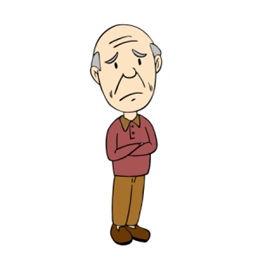肩こりについてお送りしているコラムの第4回目は先週に引き続き、具体的な原因についてご説明します。
前回は、姿勢や冷え、眼精疲労からも肩こりに影響すると説明しました。
今回は3つ目の要因として肥満、なで肩が挙げられます。
肥満やなで肩の人は、通常の人よりも抗重力筋の負担が大きいため、肩こりを引き起こしやすくなります。それらがなぜ、肩こりを引き起こすのかこの回で詳しくご説明していきます。
肥満になると、もちろん腕にも脂肪がついて重くなります。また、肥満になる方の多くは、定期的な運動をする機会も少ない傾向にあるため、抗重力筋の筋力も不足している可能性があります。つまり、単純についた脂肪の分だけ重くなった腕を吊り上げる負担と、それを支える筋力不足のアンバランスが、肩こりにつながると考えられています。
なで肩は、①単純に肩甲骨の位置が正常よりも下がっている場合、②猫背が背景にあって肩も丸くしているために肩甲骨の位置が変化している場合に分けられます。
①の場合は、抗重力筋が常に引き伸ばされている状態にあります。筋肉は引き伸ばされると、筋肉自身が通常持っている緊張が更に強くなる傾向にあり、この緊張が血流障害を招き肩こりへと発展します。
②の場合では、胴体に対して肩甲骨や腕が重力によって前側へ引っ張られる状態(抗重力筋にとっては肩甲骨と腕の重さがより強くのしかかる状態)になります。すると、より強い筋力が要求されるため、筋肉は更に強く働かなければなりません。これが筋肉の血流障害を招き、肩こりにつながります。
普段生活している中で意識を少し変えるだけで予防できることもあります。ちょっとした努力を日々行ってみてください。
次回も引き続き具体的な原因をご説明していきたいと思います。