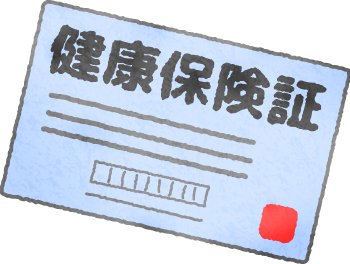column
コラム
新しい治療法 PRP療法とは?
2019/05/1
皆さんはPRP療法という治療法をご存知ですか?
PRP療法は再生医療と呼ばれる『カラダの治す力(自己治癒力)』
を利用してケガや病気を治療する新しい治療法です。
最近ではメジャーの大谷選手が行った治療法として有名ですが
このPRP療法が当院でも受けられるようになりました!
PRP療法(多血小板血漿療法)とは?
私たちのカラダの血液中に含まれる血小板の『組織を修復する力』
を利用した治療法です。
採決した血液から『組織を修復する力』の成分であるPRPを抽出し、
再び体に戻すことで炎症や傷ついた組織の治癒を促してくれます。

どんなトコロに効果が期待できるの?
主に筋肉や靭帯、腱、関節などの治癒効果が報告されています。
さらに、当院ではAPS療法といわれる次世代型PRP療法も導入しました。
APS療法は欧米で変形性ひざ関節症の痛みと機能改善が報告されており、
新たな治療の選択肢として期待されています。

今回はPRP療法についてご紹介させていただきました。
さらに詳しく知りたい方は当院ホームページまたは下記リンクをご参照ください。
関節ライフ 再生医療ガイドhttps://kansetsu-life.com/saisei/6_03.html#6_3_2
毎月の保険証確認はなぜ必要なの?
2019/04/6
病院の窓口ではみなさんが適切に医療保険制度を
利用できるようにお手伝いしております。
今回はその一つとして保険証の確認作業について
ご説明したいと思います。
みなさんは『社会保険』または『国民健康保険』に
保険料を納める代わりに1~3割の自己負担で
治療を受けることが出来ます。
残りの治療費は保険組合が支払うのですが、
その事を証明するのが保険証ということになります。
ですが、この保険証は一般的なサービス券と同じく
有効期限があると同時に、転職や年齢、収入の変化によって
窓口で支払う自己負担額が変化します。
そのため、みなさんが適正な負担額をお支払いいただくため
月々の保険証の確認作業が必要なのです。
さて、来月の診療はG.W明けの5/7(火)からとなります。
引き続き、5月分の保険証確認にご協力お願いします!
【コラム】変形性ひざ関節症とリハビリ①
2019/04/3
変形ひざ関節症
年齢とともにひざ関節が変形して『痛み』や『動かしづらさ』などの症状が出現するひざの代表疾患です。
症状
ひざの『動かしづらさ』(ひざが伸びない・曲がらない)に始まり、
徐々に動き始めや歩行時の『痛み』を感じるようになります。
類似した疾患として半月板損傷や鷲足(がそく)炎などひざの痛みを伴う疾患も
あるため、診察で確認してもらいましょう。
治療
リハビリとお薬・注射などの保存療法がメインとなります。
保存療法の効果が乏しく、症状が進行して日常生活に支障がでてきた場合は手術の選択となります。
変形性ひざ関節症は早期の治療がポイントになるため、
ひざの症状が続く場合は一度ご相談ください。
次回のコラムでは、ひざ関節症のリハビリについてお話します。
【コラム】腱板断裂④
2016/01/28
今回は腱板断裂のリハビリについてお話しさせて頂きます。
腕が挙がるためには、脊柱(背骨)や肩甲骨や鎖骨などの正しい動きが必要になります。
そのため、脊柱、肩甲骨、鎖骨がきちんと動くようになると、腕は誘導されるように楽に挙げられるようになります。
例えば、猫背のような姿勢だと脊柱、肩甲骨、鎖骨が十分に動けなくなってしまいます。
このまま無理腕を挙げたり、腕を回したりすると肩峰と上腕骨頭がぶつかり合うことになります。
そうすると、断裂した筋肉がより傷むことや、痛みがより強く出るなど様々な危険があります。
また、腱板が完全に切れてしまっていても、中には腕を挙げられる人もいます。
つまり、腱板が腕を挙げる動作のすべてを担っているのではなく、周りの筋肉も上手く使えると、腱板断裂している状態でも腕を挙げられるようになります。
ここで、自宅でも簡単にできる肩甲骨周りの筋肉のトレーニング方法を紹介します。
1.肩甲骨内転
左右の肩甲骨を脊柱に近付け、胸を張るようにするトレーニングです。
これは、猫背のような姿勢の予防、改善だけでなく、腕を挙げるときに必要な脊柱の動きの練習にもなり、比較的痛みが少なく簡単にできるトレーニングになります。

2.負荷量が高い肩甲骨トレーニング
ボールを使いながら壁を押すようにすることで、肩甲骨を安定化させる作用のある筋肉を鍛えることができます。座った状態や立った状態よりも、仰向けで寝ている状態のほうが腕が挙がりやすい場合は、肩甲骨の安定化に関わっている筋肉の機能が低下している可能性があります。そのため、肩甲骨を安定化させる作用のある筋肉のトレーニングをすることで、より腕を挙げやすくなります。
ここでは、代表的な2つのトレーニング方法を紹介しましたが、人によっては痛みが出てしまう場合もあります。そのため、一人ひとりに合った方法でリハビリを進めていくことが大切になります。
また、肩の痛みがある場合は痛みを避けようとして別の部位に過剰な負担をかけるような姿勢をしがちです。その結果、二次的な痛みを生じることもあるため、トレーニングだけではなく、ストレッチやリラクゼーションすることも大切なリハビリの一つになります。
今回で腱板断裂についてのお話しは最後になります。最後までご覧頂き、ありがとうございました。
コラム~腱板断裂③~
2015/11/28
今回は腱板断裂の治療法についてお話しします。
腱板断裂は多くの場合、外来通院での治療で症状が軽くなります。そのため手術をしない保存療法が第1選択となることが多いです。しかし、保存療法の効果が認められない場合や腱板断裂が広範囲の場合、筋力低下が著しく日常生活に不便がある場合などは手術療法を選択します。
〇保存療法
・安静…まずは痛めてしまった肩を休めていきます。腱板断裂の原因は肩の使いすぎによるものが多くを占めます。そのため無理をせず安静にし、肩を休めることも大切な治療の1つとなります。
・活動制限…肩を使うスポーツや重い物を持つなど肩に負担をかけるような活動を制限する必要もあります。また、日常生活の中では痛みのでるような動きや姿勢を避けることも必要になります。
・注射…夜間痛や動作時痛などの痛みが日常生活での苦痛がある場合や痛みによりリハビリが進まない場合などに行います。炎症や痛みが強い場合にはステロイドの注射をして、炎症や痛みを抑えていきます。
それでも炎症が残る場合、関節の動きを良くする目的でヒアルロン酸を注射することもあります。
この他に、ロキソニンやシップなどの塗り薬や貼り薬も併用する場合もあります。
保存療法にはリハビリによる治療も含まれますが、リハビリについては次回のコラムで
お話しさせて頂きます。
〇手術療法
保存療法による通院治療を行っても、肩の引っ掛かりによる痛みが取れない場合や、力が入らず腕が挙がらない場合には手術によって断裂部分の縫合をします。また、腕を挙げる動作を必要とするスポーツや仕事に復帰を望む場合にも手術を行うことがあります。
手術療法には主に①オープン法、②関節鏡法、③ミニオープン法の3つがあります。
①オープン法…歴史のある方法で、大きな断裂に選択されることが多いです。三角筋を 肩峰から切離することで直接的に腱板断裂を確認できる特徴があります。オープン法では肩峰の骨棘を切除する肩峰形成術を併用することが多くあります。オープン法は腱移行術、腱移植などを併用する場合に良い方法となります。
②関節鏡法…関節鏡というものを関節内に入れて手術を行います。モニターに映った関節内の映像を見ながら小さい手術器具を用いて手術を行います。関節鏡はとても小さいため、手術による傷も小さくなります。
③ミニオープン法…関節鏡を用いて肩峰の骨棘を切除した後に腱板を修復します。オープン法との違いは三角筋を肩峰から切離しないところにあります。
このように腱板断裂は症状により様々な治療法が選択されます。
次回は保存療法のなかでもリハビリについてお話しさせていただきます。